翌週の日曜。
僕は先週と同じようにJR中央線に乗り三鷹駅へと向かった。
それまでの一週間。
仕事をしながら、食事をしながら、煙草を吸いながら、僕は文子さんの事を考えた。
文子さんは抜け殻のようだった。
僕が会いに行ったところで、何が変わるというのだろうか。
何の意味があるのだろうか……分からない。
分からないけれど、ここで文子さんに会いに行くことを止めてしまったら、僕は一生後悔し続けるだろうという事だけは分かっていた。
施設に到着すると、事務所で面会手続きをして3階へと向かった。
エレベーターを降りると前回と同じような光景が広がっていた。

ナースステーションの前を通り文子さんの部屋に向かおうとすると、ステーション内にいた職員と目が合った。
前回僕を部屋に案内してくれた女性職員だった。
「こんにちは」と笑顔で声をかけられた。
「あ、こんにちは」と僕も笑顔を作り挨拶を返した。
職場では挨拶をしても大体黙って頭を下げるだけだった。
声を出して挨拶をして笑顔を作るなんて……決して悪い事ではないけれど、Tシャツを後ろ前に着てしまった時のような違和感をおぼえた。
四人部屋のベッド周りのカーテンは全て開けられていた。
部屋にいるのはベッドの文子さんだけだった。
丸椅子に腰かけじっと文子さんの寝顔を見つめた。
静物画のような寝顔だった。
文子さんの周りの時間だけが止まっている感じがした。

僕は枕元に近寄り呼びかけた。
「文子さん」
目を閉じたまま、静かに呼吸をしている。
「文子さん、亮です」
少し大きな声で呼びかける。
だがやはり反応はなかった。
やっぱり、という感じだった。
思っていたよりもショックはなかった。
返事が無くても、僕の目の前で寝ているのは文子さんなのだ。
文子さんと会話ができれば、それは僕にとって何より嬉しいことだ。
だけれど、文子さんにまた逢うことができた。
それだけでも、一人っ子で両親が他界してしまった僕にとっては、体の芯が熱くなるほど嬉しい事なのだ。
そう思うようにすることによって、こうあって欲しかった文子さんと、現実の文子さんとの混沌を整理して受け入れようとした。
腕時計に目をやった。
10時半。
お昼まで1時間半ある。
ショルダーバッグから「城」の写真集を取出しページをめくった。
何回も見ている写真集。
いつもはすぐに写真の世界に集中することができた。
だけれど、今回は作業的にページをめくるだけになってしまっていた。
やはり、僕の目の前にいる文子さんが気に掛かる。
そう簡単には現実を受け入れることはできなかった。

文子さんの寝顔と外の風景とを交互に眺めているうちに、昼食の時間になった。
「失礼します」ステーションの中にいた、前回と同じ女性介護士の方が部屋の中に入ってきた。
胸ポケットには石渡と書かれたネームが張られていた。
「高島さん、お昼ご飯になりますので食堂に誘導しますね」前回とは違う明るい口調だった。
「よろしくお願いします」
「あの、失礼ですが、お孫さんの方ですか?」
「あ、はい」
僕に関する質問が来るとは思っていなかった。僕は慌てて、
「文子さんは父方の祖母です。ですが、父はもう亡くなってしまっていて……」と、話す必要が無い事まで口走ってしまった。
「そうなんですか。何と言っていいのか……ごめんなさいね」そう言って僕に向いていた視線を逸らした。
「いえ、もう大分前の話なので大丈夫です」僕は努めて明るく言った。
「そうですか。いろいろ大変だったでしょうね」
「いえ。大丈夫です」なんとなく気まずい言葉の空間が開いた。
「あ、では、高島さんをお連れしますね」
そういうと、石渡さんは前回と同じように文子さんを乗せた車椅子を押して部屋を出て行った。

僕は誰も居なくなった部屋の中を暫く眺めてからゆっくりと部屋を後にした。
それから一ヶ月ほど、同じようなパターンで週末に文子さんの面会に出かけた。
10時前後にベッドサイドの丸椅子に座り、12時の昼食まで寝顔を時々眺めながら、写真集や本を読む。
約2時間の静に満たされた時と空間。
久しぶりに味わう安心感だった。
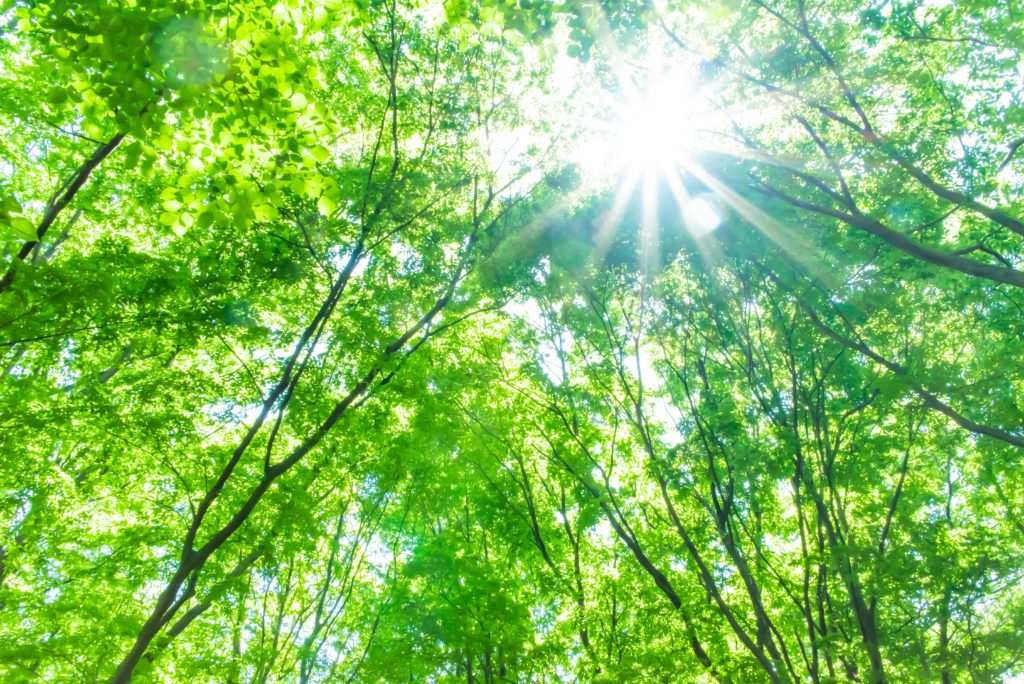
その日も12時になり、男性介護職員が文子さんを迎えに来た。
僕はお願いしますと言い文子さんに目で別れを告げ席を立った。
エレベーターに乗るためにステーションの前を通りかかった時だった。
「あの、ちょっとよろしいですか?」
ステーションの中から声をかけられた。
「お帰りですか?」そう言いながら石渡さんが歩み寄ってきた。
「はい……?」
僕は怪訝な表情で答えていた。
「あの、もしよろしければ、食事介助をしてみませんか?」
石渡さんの提案が僕にはすぐには理解できなかった。
「高島文子さんの食事介助を、ご飯を食べて頂くのをお手伝いしてみませんか?」
思いがけない提案だった。
機械的に食事をしている文子さんを見るのは辛い事だった。
だから、お昼になるとすぐに帰るようにしていた。
食事を介助している介護職員の人が悪いわけではなく、文子さんがそのようにしか食事ができなくなってしまっているのだとわかっていた。
でも、心の一部では介護職員の人たちを否定していた。
文子さんはもっと美味しそうに食事をすることができるのだ。
もっとゆっくりと、時間をかけて食事を味わってもらえばいいのだ、と。
否定しているだけだった。
僕からは何か行動を起こそうとは思っていなかった。
そんな僕に突然渡されたバトンだった。

「あ、はい」
思わずこぼれ出たという返事だった。
迷いがなかったわけではなかった。
というよりも、迷いがまず頭に浮かんだ。
『どうしよう……』と。
でも、迷いの先は肯定の返事しかなかった。
「では、こちらにどうぞ」
石渡さんは微笑むと、僕を文子さんの隣に案内した。
「この椅子に腰かけてください」
文子さんの隣に差し出された丸椅子に腰かけた。
「今日は、私が隣の方の食事介助をしながら、お二人の様子を見て対応しますので安心してください」
「はい」
「文子さんのお食事はお粥とキザミ食です。
これじゃ何を食べているかわからないですよね……。
でもね、こういう形態じゃないと、文子さんは噛む力と飲み込む力が弱くなってしまっているから、上手に食べることが出来ないんです」

「そうなんですか」
「だからせめて、味は分かって頂けるように、刻まれているおかずが混ざらないように食べて頂くようにしているんです」
ゆっくりと少しずつ、飲み込むのを確認してから食べて頂くようにしてくださいと言い、石渡さんは実際に文子さんに数口食事介助を行った。
「では、お願いします」
僕の右手にスプーンが手渡された。左手でお粥の入った食器を触ってみる。
温かいというか、ややぬるくなっている感じだった。
スプーンに半分ほどお粥を掬い、文子さんの下唇に軽くあてる。
すると文子さんは小さく口を開いた。
その中にそっとスプーンを滑り込ませ、お粥を舌の上にそっと置くように流し込んだ。

スイッチが入ったように機械的に口をモグモグとさせ咀嚼をし、ゆっくりと飲み込んだ。
「うん。大丈夫そうですね。その感じで続けてください」
「はい」
文子さんの口元、のど元、表情を観察しながら注意深く食事介助をおこなった。
文子さんはとてもゆっくりと食事をした。
もともとおっとりとした性格で、動作は早い人ではなかったけれど、それとはまた違うゆっくりさだった。
文子さんは何を食べているのか分かってはいないだろう。
そもそも、食事をしているという認識はもうないのかもしれない。
でも、だからと言って空の容器に燃料を注入するように機械的に行ってはいけないのだ。
それは何故かと尋ねられても僕には理論的には答えられない。
でも感覚的に今まで苦労をして精一杯生きてきた人間に、物を扱うような対応をしてはいけない、最後の時まで人として対応しなくてはいけないのだという思いはあった。
そして今、目の前にいるのは、僕の原風景に絶対的に必要な文子さんなのだ。
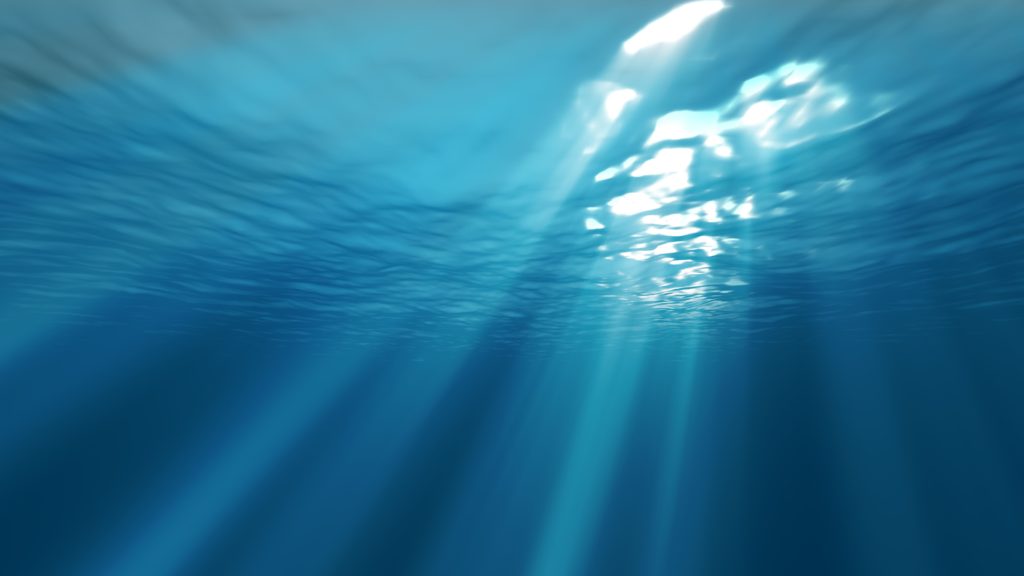
最後にマグカップに一口ほど残ったお茶を飲みほし、文子さんの食事が終わった。
周りを見渡すともう他のお年寄りの方々は全員食事を終え、口腔ケア(入れ歯の洗浄や歯磨き)をおこなったり、お部屋に戻ったりしていた。
壁に掛けられた時計を見てみると40分程の時が流れていた。
「終わりましたか?」口腔ケアの介助をしていた石渡さんが歩み寄ってきた。
僕は安堵の笑顔で答えた。
「お疲れ様でした。高島さんもゆっくりと食事ができて良かったと思います」
「はい。そうだといいのですが」
「高島さんはこれから少しここで休んで、そのあとお部屋に戻ってベッドで休んでいただきます。
すぐに横になると、もどしてしまうことがあるんです。それは高島さんに限らずなんですけれどね」
「僕はこれで失礼します。色々と有難うございました」
「正直、私たちも助かるんです。介護の現場は常に人手不足ですから。
本当はもっとゆっくりと、丁寧な対応でお年寄りの方々に接したいと思っているんです。
でも、目前のこなさなくてはならない仕事につい流されてしまって……常に葛藤しているんです」
「皆さん、とても忙しそうですよね」
「あ、すみません。ご家族の方にこんなお話をしてしまって」
「いえ」
「では、お気をつけてお帰り下さい」
僕は文子さんの手に触れて別れを告げ、エレベーターへと向かった。


